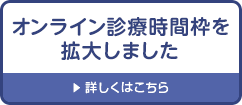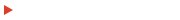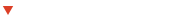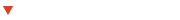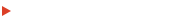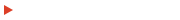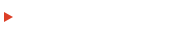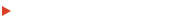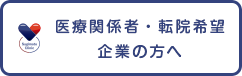抗甲状腺薬
抗甲状腺薬(メルカゾール、プロパジール、チウラジール)の副作用について
副作用は内服開始後2~3ヶ月以内に起こることがほとんどで、その間は2~4週に一度副作用がでていないか診察で確認します。それ以降は副作用の頻度はかなり低くなります。
いずれの副作用も適切に対処すれば問題ありません。しかし無顆粒球症候群や重度の肝障害は対処が遅れると生命にかかわる危険なものです。またメルカゾールに関しては、胎児の奇形との関係について留意する必要があります。
無顆粒球症候群
白血球の中の顆粒球が極度に減少する、最も注意が必要な副作用です。細菌に感染しやすくなり、敗血症などの感染症をおこします。副作用の頻度は約300人に1人で、まれにしか起こりません。内服を始めてから3ヶ月以内に起こることが多く、内服を始めてから2週間以内や長期間内服を続けている場合には起こることはほどんどありません。ただし長期間内服していた方であっても、一定期間内服を止めて再び飲み始めたときは起こることがあります。
初期症状として、風邪様症状(発熱、のどの痛み、全身倦怠感)等がでます。このような場合は直ちに内服を中止し受診してください。夜間などの診療時間外は、内服を中止して翌日必ず受診し、翌日が休日などの休診日の場合は救急医療機関を受診してください。
治療は、無顆粒球症であれば入院加療が必要となります。顆粒球が低下していない場合は、通常の風邪治療などを行います。
薬疹
最も多くみられる副作用で、かゆみのある赤いブツブツがでます。内服を中止し、1週間以内に受診してください。ただし症状が強い場合はできるだけ早めに受診してください。
治療は、軽傷の場合は内服を中止するか、抗ヒスタミン薬を内服するだけでおさまります。中等症以上の場合は副腎皮質ステロイド薬の内服を行います。
肝障害
軽度の肝障害であれば、自覚症状はなく血液検査で確認が必要です。中等症以上であれば、嘔気や食欲不振、倦怠感、黄疸などが症状として現れます。 このように症状だけでの判断は困難ですので、早めに受診して検査をうけてください。
その他の副作用
発熱、関節痛、血尿、低血糖発作、再生不良性貧血などがありますが、いずれも頻度としてはまれです。また、ほとんどの場合は内服を中止すると回復します。
メルカゾールと胎児の奇形との関連(女性)
メルカゾールを妊娠初期に服用していると、その児にメルカゾールに関連した奇形に生じる可能性があり、その頻度は2%程度です。妊娠を計画中、または妊娠の可能性がある方は必ず申し出てください。抗甲状腺薬の内服が必要な場合はプロパジールを内服していただきます。
甲状腺ホルモン剤
甲状腺ホルモン剤(チラージンS)の服用について
甲状腺機能を正常にするのに必要な量を内服している限り副作用が出ることはなく、薬として内服した甲状腺ホルモン剤と、甲状腺が体内で作る甲状腺ホルモンには違いはありません。
一方、甲状腺ホルモン剤の吸収を妨げたり、代謝に影響を与える食品や薬剤などが知られています。これらが影響すると、甲状腺ホルモン剤を指示された通りに内服しても、甲状腺ホルモンの効きが悪くなることがあります。
甲状腺ホルモン剤の効きを悪くする因子及び薬剤
1. 消化管内で甲状腺ホルモンと結合してその吸収を妨げる
- 高食物繊維食品:野菜ジュース、青汁、ダイエット食など
- コーヒー
- 脂質異常症治療薬:コレバイン、クエストラン
- 胃薬:アルサルミン、マーロックス、キャベジン、プロマックなど
- 貧血治療薬:フェロ・グラデュメット、フェロミア
- 過敏性腸症候群治療薬:コロネル
- 慢性腎不全の治療薬:沈降炭酸カルシウム、レナジェル、ケイキサレート
2. 胃酸分泌低下による吸収不良
- 胃薬:オメプラール、タケプロン、パリエットなど
- 慢性胃炎などによる胃酸分泌低下
3. 吸収不良を起こす疾患
- 腸粘膜の病気や腸の切除後
4. 吸収を妨げるが、その仕組みは不明
- 抗菌薬:シプロキサン
- 骨粗しょう症治療薬:エビスタ
5. 甲状腺ホルモンの必要量が増加する
- 妊娠
- 女性ホルモン剤:エストロゲン
6. 甲状腺ホルモンの分解を早める
- けいれん治療薬:アレビアチン、ヒダントール、テグレトール、フェノバール
- 結核治療薬;リフェジン
7. T4からT3への代謝を減少させる
- 抗不整脈薬:アンカロン
※1の食品や薬剤はそれらと一緒に甲状腺ホルモンを内服しなければ問題ありません。時間をずらして内服すればよいので、夕食時間と就寝時間までの間の時間が長い方は、甲状腺ホルモン剤は就寝前に、起床時間から朝食時間までの間の時間が長い場合は、起床時に内服するのがよいです。
それ以外の場合は、内服時間をずらしても、影響を軽くする効果はあまりないかもしれません。